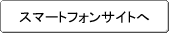|
|
|
【愛】
・愛とは信じること
・愛するとは許すこと。
・愛とは、相手の短所を許し、補い、長所とかかわる力。
・愛とは肯定すること。理屈を超えた肯定の心
・愛とは認めること
・愛とは相手の成長を願う心情
・新しい精神文明の核となるもの
・愛は理屈を超える力。
・愛とは人間と人間を結びつける力。
・愛とは他者と共に生きる力
・愛とは他者中心的な心の働き、思いやりである。
・愛とは「どうしたらいいのだろう?」と悩む心、考える心。
・相手のために努力できるということが「愛」があるということ。
相手のために努力できないのは「愛」がないということ。
・愛は人間関係の力である。人間関係の基本は愛。
・結婚は恋の墓場であり、愛の始まりである。
・人間を愛するというのは不完全な存在を愛するということ。
不完全とは、どんな人間でも長所半分・短所半分。
・自分と同じ考え方の人しか愛せないのは、偽者の愛。それは自分しか愛せない愛である。
・愛は本来、他者を愛するために存在する。
・愛とは 命の能力である。
・命は愛によって生み出され、育まれ、満たされる。
・愛とは他者中心的な心の働き、思いやりである。
・愛は理性を使った努力。
・愛するとは、相手から学ぶこと。
・包容力は、愛。
・愛とは、今、一番人類に必要とされている能力
・愛とは、人間が努力してつくっていく文化
【愛の最終目的】
素晴らしい人間関係を創造する力をつくっていくこと
【愛の実力】(人間関係 10の原則)
●良い人間関係をつくっていく5つの実力
1.人間への深い理解
2.理性の謙虚さ
3.人間に完全性を求めてはならない
4.競争原理を捨てること
5.ユーモアのセンス
●悪化した人間関係を修復する5つの実力
1.どんな人でも好きになる実力
2.どんな人からも好かれる実力
3.対立を乗り越える実力
4.問題解決の実力
5.真実への勇気
【悪】
悪というのは、そういう人間の不完性から出てきているもの。
悪というのは、今、この現実において何が問題なのか、
現実のどこに問題があるのかを人間に気づかせてくれる現象。
【生きている】
変化すること。変化しないということは死んでいるということ。
安定しているとは、動かないことではなく、揺らぎながらバランスをとっていること。
いろいろな問題が出てきてもそれを解決して、元に戻す力があること。
【意志】
・自己保存欲求が、人間化され、理性化されて形成されるもの
・自己実現の力
・意志と意思
【意志と愛】
・意志とは、自己保存の欲求。仕事において成功すること。
・愛とは、種族保存の欲求。人間と人間を結びつけるもの。
すばらしい人間関係をたくさん作ること。
【意志と意思】の違い
思いだけでは、浅い。「志」にならなければいけない。
【意志の強さ】
・心のそこから湧いてくる興味関心欲求欲望が強いこと。
「がまん強い」ことではない。
がまん強さは、理性的な強さ。
【一道一徹】
一つの道を貫き通す
【一燈照宇の志】
たとえ一本のロウソクでも身の周りを照らせば明るくなる、
それを万人が照らせば「万照」、ことごとく世界を照らせば「遍照」。
全ての始まりは常に小さなところから。
ひとつの灯火が片隅を照らす。
その灯火が次の灯火を点け、また次の灯火を点ける。
そして多くの灯火が全国を照らし、ひいては地球を照らす。
<参考>「一燈照隅、萬燈照国(ばんとうしょうこく)」
「一燈照隅」とは、「一隅を照らす」ということ。
「一隅」とは「今あなたのいる場所」、自分が今置かれた場所で精一杯努力し光り輝くこと
【命】
命の根底には、感性がある。
感性が肉体の形を決定し、精神を作っている。
【命より大切なもの】(死にうるものとの出逢い)
「このためなら死んでもいい」「この人のためなら、命をかけても守る」、
「この仕事になら、命をかけて取り組める」と思えるものと出会ったとき、
命は最も激しく燃え上がり、最高に輝く。
「この人のためになら死んでもいい」と思うくらい人を愛さなければ、
本当の意味での愛のすばらしさを味わえない。
相手からも「この人のためになら死んでもいい」と思ってもらえるような人間に
なるための努力をし続けることも大切。
仕事でも、「この仕事のためになら死んでもいい」と思うくらいでなければ、
本当の意味での仕事の醍醐味を味わっていない。
理屈を越えたものであり、命のそこから湧き上がってくるもの。
理性で考えるものではありません。
命には、命より大切なものがある。
【異和感】
・辞書では「違和感」
・「違い」を理由に相手を説得したり、攻撃したりする。 違うのではなく、「異なる」だけ。
・「異なる」ものから、いいところを学び、自分の考えを成長させる。
・自分のもっている能力が、今あるものよりすぐれていることをあらわすもの
【宇宙】
エネルギーバランス。
宇宙はプラスのエネルギーとマイナスのエネルギーがお互いに
バランスを模索しながら形成されている。
【会社】
・会社は、すべての人間にとって最大の生きがいの原点であるべき。
職場という最高の自己実現の場、自分がその仕事を通して自分を完成させていく場、
自分をつくり出していく場、自己創造、自己完成、自己実現の
最も素晴らしい世界でなければならない。
・会社は、全社員が自分の能力を最大限に発揮できる最高の場所だと
言えるような喜びを与えてやらなければならない。
社員一人一人が、この会社こそまさに自分の能力を最高に発揮できる場所だと
言えるような仕事を経営者は与えてやらなければならない。
自分が最高に活かされる状況を全社員に創ってやる事が理想であらねばならない。
・会社の本当の目的は、勝つ事ではなく、成長する事。
勝つ事は、成長するための1つの方法であるということ。
勝つ事で成長する時代は終わっている。
【器】
どんな人のことでも誤解することなく理解する能力と人間性
【顔】
似ていても、全く同じ顔はない。
それは、「世界中で、自分しかできないことがある」ということの証明。
能力とは、遺伝子が顕在化したもの。
子供には、両親を越える潜在能力が眠っている。
なぜなら、二人の遺伝子を引き継いでいるから。
【科学】
・もっとよく知りたいという欲求、認識欲を実現するために人間が考え出した学問
・「もっと良く知りたい」という欲求と知識欲に応えるのが科学・サイエンス
・人間が真剣になって本当に生きようと思ったら、存在の事実・現実の中にどういう事実が
存在するのかをどうしても知りたくなる。その追求を担うのが科学。
・理論を武器として現実の中の事実を対象にし、その構造や法則という真理を探究する。
その方法は実証的。
・科学は現実の中の事実を対象とし、現実の世界に存在する物事の構造と法則を真理として探究する。
すでに存在する事実を解明・探究する発見的な学問である。
・事実には、過去と現在しかない。未来に対応する能力はない。
【科学と哲学】
学問は、科学と哲学に分かれる。科学は発見し、哲学は創造する。
科学が理論・セオリーを方法とし、哲学は論理・ロジックの方法を用いる。
哲学と科学は互いに協力し合いながら、
現実から理想へという人類の生き方に貢献する。
【角熟】
・短所を人間の味に変えていく、
そして短所の自覚が人間に謙虚さをつくってくれるという状態
・個性ある人間の理想の状態
・個性のある本物は、角張ったまま熟していく。
角張ったまま熟していくところに、個性のある本物の人間の姿がある。
【活人力】
自らの短所をさらけ出すことにより、他人の長所を生かし、人を輝かせる力。
短所ばかりでは、人に助けてもらう事はできない。
自分も長所を生かして、他人の短所を補ってあげること。
ただし、助けるときは、黙って助ける。
助けてもらえるような人間性をつくる事も大切。
助けてもらう事は、助ける事と同じくらい価値がある。
【神】
・「神」は、存在するか存在しないかの問題ではない。
『「神」という言葉が存在する』
目に見えない、人間の力ではどうすることもできない。
大きな存在があることをあらわしている。
・目に見える現実の背後に、目に見えざる何かがあることを人類は、
神という言葉を持つことによって意識し始める。
そこからはじめて、人間は歴史をつくることができるようになった。
・神という言葉を持ったことは、人類史上、画期的な出来事。
旧人と新人をここを原点にして分かれる。
【感性】
・感性論哲学は、「感性」をベースに組み立てられた学問。
・人間は、「感性」と「理性」と「肉体」からできている。
「理性」を否定するものではない。感性と理性の協力関係が大切。バランスではない。
感性だけで行動するのは、ただの野獣。
命の底から湧いてくるものを理性を使って人間らしくする。
・「感受性」よりも「求感性」(ぐかんせい)求めなければ受け取れない。
感性の本質は、求感性。
・動物も植物も単細胞生物のアメーバやゾウリムシだって感性を持って生きている。走性
・感性は生命を貫く原理。
・感性は全生物がみんな持っている生命の本質という能力。
・感性は生命の本質
・瞬間というものは感性でしかつかめない。
・生きているものを生きているままでつかもうとすれば、
感性というものを使わなければならない。
・大宇宙から人間に与えられたものは、
大宇宙から人間に与えられた先天的な生来の能力である
肉体と感性を使わないとわからない。
・やってみて好きになるかどうか。やってみるということは肉体を使うこと。
好きになるかどうかというのは感性を使うということ。
・納得する力。納得とは腑に落ちる状態。
・感性を原理にして生き始めると、理屈を超えた行動ができるようになる。
【感性の3作用と真善美】
・合理作用・・・真・・・時間バランスや時間的速度追求や論理性に働く作用
・調和作用・・・善・・・空間バランスや形をよりよくする作用
・統一作用・・・美・・・とりまとめて新しい平衡状態をとる作用
【感性型リーダーシップの10の条件】
1.教育力・活人力・・・人に教えることのできるずば抜けた能力・人の持っている能力を使う活人力
2.魅力的な個性・人望・・・人間的魅力・人望・人格があるか
3.勇気ある行動力・・・勇気ある行動力をもっているか
4.先見力・・・歴史観に基づいた先見性をもっているか
5.夢を語る力・・・情熱を持って夢を語れるか
6.哲学を持つ・・自分の生き方を支える自分の哲学(マイフィロソフィ)をもっているか
7.成長意欲・向上心・・・人間として成長意欲をもっているか
8.創意工夫・・・創意工夫の精神があるか、出来上がっているものを破壊する勇気があるか
9.文化力・・・文化力を身につけているか
10.人間性の豊かさ・・・包容力に富んでいるか・人をまとめていく統率力があるか
【感性型フォロワーシップ】
リーダーが知っておかなければならないフォロワーの条件。
リーダーは、フォロワーにこれを強制してはならない。
「フォロワー」とは、どうあるべきかを知り、片腕を作り上げるための指針とするもの。
<感性型フォロアーシップ10の条件>
1. リーダーの夢をわが夢としているか(夢の共有ができているか)
2. リーダーにとっての名参謀に徹しているか
3. フォロワーの気持ちをリーダーに素直に伝える・教える・語る
4. リーダーを育て、成長させる
5. リーダーの短所を補い、責めない
6. 理屈を超えてリーダーに従い、リーダーを守る
7. 仕事を通じて、自己を成長させる
8. 人の役に立つ、人に必要となる人間となる
9. 会社の中での地位や立場・役割を自覚して働く
10. 今、自分のしていることの意味や価値を確認しながら働く
【感性経営の5原則】
・第1原則・・・利益の出る仕組みをつくり続ける
・第2原則・・・よりよい方向性へ変化し続ける
・第3原則・・・問題を乗り越え続ける
・第4原則・・・感性から湧き出した理念を大事にする
・第5原則・・・本業を通して会社と社員を発展成長させる
【感性的判断能力】
・いい感じか、悪い感じか
・好きか、嫌いか
・快か、不快か
「理性的判断基準」とは、「損か得か」「正しいか間違いか」
理性的判断基準が悪いと言うことではない。
【感性文明】
・物質文明を否定しない精神文明の創造
・物欲を、人間的に品格のある洗練されたものにしていこう、という努力が、
文化や文明を発展させるための原理なのです。
文化、文明は、正に物欲の洗練化されたもの。
【感性論哲学】
感性論哲学の創始者・芳村思風先生が、「感性」をベースに創造し体系化し、成長させた哲学。
「感性が人間の本質であり、感性が生命の本質であり、感性が宇宙の究極的実在である」
という考え方にのっとって、人間の生き方・社会の在り方・経営の仕方・政治の在り方・
教育の問題・歴史観・文化芸術の問題などを考えていくのが感性論哲学の体系。
実践哲学であり、その現実的かつ実践的な柱は、「意志と愛」
感性論哲学は、『意志と愛の哲学』
『感性論哲学は、なにも否定しない。それ故に感性論哲学は科学技術文明も否定しない。
問題は、その上にいかなる文明を積み重ねていくかである。
感性論哲学は、人類普遍の実感、感動に内在する存在論的実質を原理として重視する』
【感性論哲学の基本原理】
●感性論哲学 基本的3つの原理
・人間観の革命と呼んでいる新しい人間観
・生命観の革命と呼んでいる新しい生命観
・宇宙観の革命と呼んでいる新しい宇宙観
【感性論哲学の目的】
全人類の人間性の成長
【感性論哲学の基本的な考え方】
理性によってつくり出された目的は、人間を縛るものであって、窮屈で堅苦しい生き方を人間に
要求する。「命から湧いてくる欲求」を実現するところに自由があり、開放感があり、喜びがある。
【感性論哲学宣言】
人間存在は単なる精神と肉体の結合ではなく、存在論的体系としては、感性によって根元的に
結合統一され、生かされている有機体であるという新たなる人間観は、少しずつ学会にも
認められつつありますが、なおかつ認識論的知識優先の理性主義の立場からは、
保守的なの抵抗が根強く見られます。
しかし、感性こそ生命の本質であるという思想に立つ人間観と「感じる力」の活性化と積極的活用こそ、
これからの人間の最も必要な人間性であるという、この新しく切り拓かれた人間進化の地平に
間違いないと確信しております。
小生はこれからも生のあらん限り感性を原理とした人間と社会のよりよい在り方を探求する活動を
続けて死んでいきたいと考えております。
小生の力は微力でもこの思想は、きっと将来の人類の宝となると信じております。
(行徳哲男先生に送られた手紙より)
【教育】
教育の目的は、人間らしい心を持った人間を作ること。
人間らしい心を持った人間とは、次の3つの条件を満たす人間である。
1.不完全性の自覚からにじみ出る謙虚さを持っているか。
2.より以上をめざして生きるという人間としての成長意欲を持っているか。
3.人の役に立つことを喜びとする感性を持っているか。
わからない子どもを解るようにすること。できない子どもをできるようにすること
今までの教育は「人材教育」、これからは「人物教育」が必要。
【教育の方法】
感性を人間化させるための手段能力として理性を使うことである。
教育の理念は、育てる為に、教えるということである。 教が、育を超えてはならない。
人間らしい心を作る最も本質的なものは、価値を感じる感性である。
【教育力】
子供が理解できないは、今の話し方・説明のしかたでは伝わらないということで、
自分の話し方・説明のしかたが悪いということ。
「どうしてわからないのか」ではなく、「どうしたらわかってくれるか」を考えることが大切。
【教育論概論】(目次)
・教育の目的と方法と理念
・動植物からも学ぶ必要がある
・教育の領域
・教えることは教えること
・教育とは、「やったぁ!」という感動を味あわせること
・知育・徳育・体育という3つの観点から考える
・人間らしい心を創る最も本質的なものは、価値を感じる感性である。
・理性という能力を、関心や欲求を呼び覚ますために使って教育する。
・子供を育てる自信がもてない状況
・価値への感覚が、人生とどう関係しているかを教えること。
・教育力を取り戻す。
・教が育を超えてはならない。
・自分がその頃どうであったかという事を思い出しながら教育する。
・子供は空なる気を吸って育つ。
・親や教師や教育する側の生きる姿勢。
・自分が引き受けて立つ。
・勝つことよりも、もっと大切なことは、力を合わせることである。
・対立して自己を主張することは、無能な個性の証明である。
・人間性の豊かさとは何か。
・人間は、誰でも見たがり屋で、聞きたがり屋で、触りたがり屋である。
・いい感じか、悪い感じかということが、人間的総合判断である。
・創造力・時流独創の精神を創るには。
・悔いのない人生とは。
・生きがいと人生の目的とは。
・宇宙の摂理と人生について。
【境涯論】
境涯とは、人間的な幸せを手に入れる成長過程の段階
【共感能力】
相手の喜怒哀楽の感情を感じ取る能力
共感同悲・共感同苦・共感同喜
【求感性】
感性の本質。求めなければ受け取れない。
自分が生きて行くために必要な情報を自ら感じ取ろうとする感性の働き
自分の心を本当に納得させてくれるものを求める力。
本当に納得させてくれるものとは、「真実」であり、「感動」
【経営】
より良い方向性への変化作り出し続けること。
経営者にとって、大切な経営能力は、よりよい方向性への変化を作り出し続けることによって、
社員に未来への夢と希望を与えること。
経営者は、仕事をしてはならない、経営をする。
【経営理念】感性論哲学から見た経営理念
基本理念「すべてはお役立ちのために」
行動理念「最高の満足を与え、最大の信頼を得る。そのために努力しよう。」
・問いの形の理念
問いの形にすることで固定化させない。理念は不変でなくてもよい。
答えを持つ。答えに縛られない。よりよい答えを求め続ける。
【経験】
体験…肉体を通して学んだ事実
経験…経験から学んだ知恵
【決断】
決断とは、捨てる勇気
決めるだけでは、ダメ。選び取らなかったすべてのものを断ち切ること。
人間は、不完全。どの道を選んでも問題は出てくる。
大切なことは、選んだ道に出てくる問題を乗り続けること。
「決」・・・多くの可能性の中からあるひとつの存在を選び取ること。
「断」・・・ひとつの道を選んだならば、同時に他の道への思いを断ち切ること。捨てる勇気のこと。
【現実】
事実と意味から成り立っている」
「現実」の「現」は時間、「実」は空間を意味する。
時間と空間が、現実を構成する基本要素。
【現実への異和感】
・自分に与えられた使命が何であるかということを教えてくれる現象
・感性の実感
・現実と深くかかわることによって、現実によって呼び出されてくる自分
・現実というものと深くかかわって真剣な生き方をしていなければ出てこないもの
・自分そのもの
・真剣な命の叫び
・自分に問題を課する現象
・自分の使命を自分に教えてくれている天の啓示
・「自分はいったい何をしてこの時代を一歩前に進めたらいいのか」を教えてくれる現象
・本気になって何とかしようとすれば、必ずできる能力を持っていることを、教えてくれる出来事
・何をするために生まれてきたのか、与えられた使命が何であるのかを教えてくれるもの。
・自分がなぜここにいるのかという存在理由も教えてくれるもの。
・本気になって自分がそれをやろうと思えば、現実を動かすことができる能力を、
すでに潜在能力として与えられているのだということも自分に教えてくれるもの。
・天啓の一瞬。
【恋】
・恋は、生物学的には“種族保存”のための生殖欲求に導かれた欲望。自己中心的な感情。
愛は、他者中心な感情
・恋は、自然発生的なものであって、原理的には生殖本能という生理的欲求に基づいて出てくる心情。
【志】
感性から沸いてきた欲求を、どうしたら他人に迷惑をかけずに、人の役に立つ方法で
実現できるかを考えること。
意志に社会性を加えることで、志になる。
意思→意志+社会性→志
【個性】
今時分が持っている理性能力を使っても乗り越えられない問題が起こったとき、
命の底からわきあがってきた知恵・気づき・工夫・天分・潜在能力が作る。
【言葉】
新しい言葉が、新しい価値を作る。
言葉には力がある。